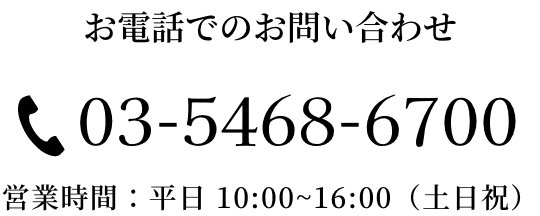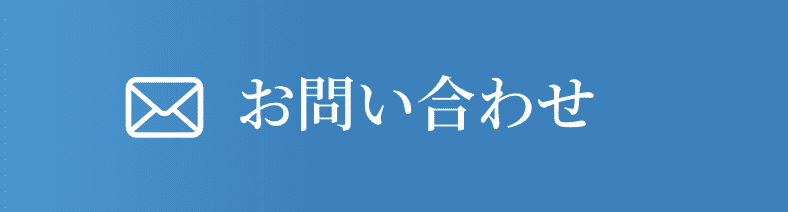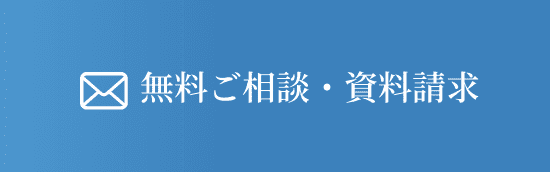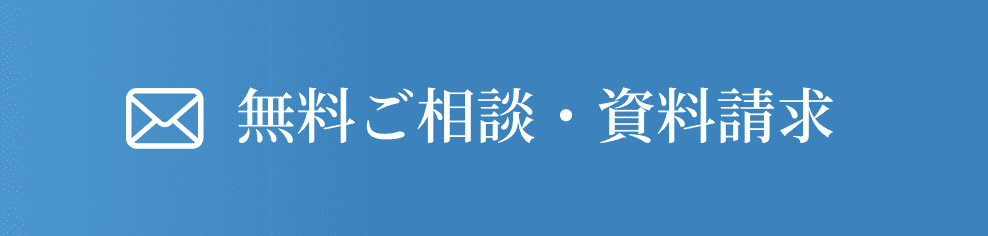講演会情報
SEMINAR
各種勉強会、講演会の
講師を承っております。
2~3時間程度のものから、
1日~数日研修に至るまで、様々なニーズに
お応えできるものと思っております。
最近の講演テーマを
資産税関係に絞ってご紹介します。
LECTURS
過去の講演会一覧
-
定期セミナー開催のご報告
講演会内容
日時:令和7年9月3日(水)
会場:セルリアンタワー東急ホテル
内容: 第1部 「なっ得!賃貸不動産の損害保険を賢く学ぶ。
~【おまけ】今更きけない「ドル建保険」って? ~」
保険サービスシステムHD株式会社 部長 桝井 孝昌氏
第2部 「最近あった興味深い相続税税務調査事例~ 人が亡くなった後、いろいろあります ~ 」
代表社員 税理士 高木 康裕


-
定期セミナー開催のご報告
講演会内容
日時:令和7年2月5日(水)
会場:セルリアンタワー東急ホテル
内容: 第1部 令和7年度税制改正の概要
税理士 沼田 八千代
第2部 原点回帰!法人活用を総点検
代表社員 税理士 高木 康裕 -
定期セミナー開催のご報告
講演会内容
日時:令和6年9月11日(水)
会場:セルリアンタワー東急ホテル
内容: 第1部 最新不動産コンサルティング事例紹介~貸宅地の権利調整、物納、土地活用、建築など~
株式会社イデアルコンサルティング 代表取締役 立花 弘之 氏第2部 最近の相続いろいろ話します~延納・遺言・税務調査~
代表社員 税理士 高木 康裕 -
税制改正を徹底解説!これから求められる相続対策とは
講演会内容
Ⅰ.令和5年度税制改正のポイント
1.暦年課税贈与
2.相続時精算課税贈与
3.その他の改正
教育資金に係る一括贈与の非課税措置の見直し
1.現行制度の概要
2.改正内容
結婚・子育て資金に係る一括贈与の非課税措置の見直し
1.現行制度の概要
2.改正の内容
4.今後の資産税の方向性
Ⅱ.相続対策に向けて
1.資産の変動を反映
2.分割方針の変更を反映
3.相続税への対応
4.いつ見直すか
-
税務面から考える!各対策別のメリットと留意点
講演会内容
Ⅰ.老朽化物件の対策
Ⅱ.改修・建替え・組換えの概要
1.相続税のポイント
2.所得税(法人税)のポイント
3.消費税(事業用)のポイント
4.固定資産税のポイント
5.登録免許税・不動産取得税のポイント
Ⅲ.改修の税務ポイント
Ⅳ.建替えの税務ポイント
Ⅴ.組換えの税務ポイント
組換え時の特例
① 居住用財産の買換特例
② 事業用資産の買換特例(法人も制度有)
③ 等価交換(立体買換)の特例
-
税理士が考える円満相続への必要な準備とは
講演会内容
Ⅰ.相続税を取り巻く環境
Ⅱ.相続財産の現状把握
Ⅲ.遺言を活用しよう
Ⅳ.信託の活用
Ⅴ.不動産を活用した相続対策
-
税務勉強会
講演会内容
1.確定申告
2.所得の種類
3.不動産所得の事業的規模
4.不動産所得 損失の制度
5.消費税
6.不動産の譲渡
7.居住用財産の3000万円控除(自宅の売却)
8.空き家の3000万円控除(相続した戸建空家の売却)
9.居住用財産の買換え
10.事業用資産の買換え
-
相続対策に本当に必要な準備とは?
講演会内容
Ⅰ.相続税を取り巻く最近の状況
Ⅱ.相続税の計算の仕組み
Ⅲ.相続対策の考え方
Ⅳ.資産整理の重要性
-
定期セミナー開催のご報告
講演会内容
日時:令和6年2月9日(金) 会場:セルリアンタワー東急ホテル 内容: 第1部 令和6年度税制改正の概要 税理士 齋藤 英寿 第2部 貴方に最適な税対策は?組み合わせ次第でいろいろできる! 代表社員 税理士 高木 康裕 -
定期セミナー開催のご報告
講演会内容
日時:令和5年9月13日(水) 会場:セルリアンタワー東急ホテル 内容: 第1部 令和3年民法等改正、及び、相続土地国庫帰属法のポイントについて 新青山法律税務事務所 弁護士 播磨 鉄治 氏 第2部 タワマン節税は本当に終了? 代表社員 税理士 高木 康裕 第3部 お一人様の相続~億万長者になりそこなった税理士の話~ 代表社員 会長 税理士 阿藤 芳明
-
定期セミナー開催のご報告
講演会内容
日時:令和5年2月8日(水) 会場:セルリアンタワー東急ホテル 内容: 第1部 令和5年度税制改正の概要 税理士 増田 優樹 第2部 精算課税贈与は使わなきゃ損?暦年課税贈与とはどう使い分けるか. 代表社員 税理士 高木 康裕 -
世間の常識、税務署の非常識!
~世間の考え方とは異なる、税務署独自の考え方を学んで税務調査に臨もう!~
~敵を知り、己を知れば百戦殆うからず~講演会内容
Ⅰ.生前贈与は6年で時効は完成か?
1.贈与の事実はいつ発覚するか?
2.贈与か貸付か
3.マイナンバーの導入でこう変わる!
4.贈与の有効性の判断
5.税務署が更正できる条件とは?
Ⅱ.海外資産があれば、それだけで税務調査の対象に?1.国際税務専門官の登場
2.難しい海外財産の時価評価
3.知らなかったでは済まされない税理士の責任
Ⅲ.”庭園”の評価はどこまで必要か?
1.「庭園設備」評価の考え方
2.財産評価に対する税務職員の視点(実例で考えよう!)
3.資産計上が必要な庭園の範囲
Ⅳ.調査の過程で「一筆書け!」は拒否できるのか?
1.調査において、よくある調査官の脅かし!
2.税務署による税理士の管理・監督
3.税務署を信じてはいけない
Ⅴ.借地権がタダで返ってきたら「贈与」になるのか?
1.税法の規定と実務の実態
2.事例の検討(1)
3.事例の検討(2)
Ⅵ.税務署に騙された事例 -
不動産”所有型法人”と信託
講演会内容
Ⅰ.何故”所有型法人”なのか
1.従前の管理型法人とその問題点
2.法人の”実態”を作る方策
Ⅱ.所有型法人の問題点
1.問題の所在
Ⅲ.どんな法人(会社)を作るか?
1.出資金と贈与
2.役員報酬の考え方
Ⅳ.所有型法人の効果(メリット)
Ⅴ.所有型法人の注意点
Ⅵ.信託の活用を考える -
税務勉強会
講演会内容
Ⅰ.住宅取得に係る主な税制
1. 住宅ローン控除
2. すまい給付金
3. 住宅取得等資金贈与
4. 上記税制のまとめⅡ.小規模宅地の評価減の特例
1.制度の概要
2.2世帯住宅の取扱い
3.被相続人が老人ホームに入った場合の注意点
-
徹底解説! これからの資産承継術
講演会内容
Ⅰ.税制改正の概要とその対応
1.所得税関係
(1)三世代同居改修工事の特別控除
(2)医療費控除のOTC控除
2.資産税関係
(1)空家に係る譲渡所得の特別控除
(2)贈与税の配偶者控除の改正
3.法人税関係
(1)法人税率の引下げ
(2)減価償却制度の見直し
Ⅱ.タワーマンション節税の行方は?
1.問題の所在
2.過去の否認例
3.改正の方向性 -
賃貸用建物の法人所有化で所得税、相続税はこんなに有利!
講演会内容
Ⅰ.何故”所有型法人”なのか
1. 従前の管理型法人とその問題点
2.法人の”実態”を作る方策
Ⅱ.所有型法人の問題点
1.問題の所在
2.建物贈与との比較
Ⅲ.どんな法人(会社)を作るか?
1.出資金と贈与
2.役員報酬の考え方
Ⅳ.所有型法人の効果(メリット)
Ⅴ.所有型法人の注意点
Ⅵ.相続後の対策 -
大増税時代を乗り切るための資産承継術
講演会内容
Ⅰ.税制改正の概要
1.所得税(1)NISAの再開設・再設定と金融機関の変更
(2)取得費加算の特例の改正(譲渡税)
(3)ゴルフ会員権等の譲渡損の取扱い
(4)給与所得控除の見直し
2.相続税
(1)2世帯住宅に係る小規模宅地の特例
(2)老人ホームと小規模宅地の特例
3.法人税
1.復興特別法人税1年前倒し廃止
2.交際費の限度計算
4.消費税
Ⅱ.信託の活用
1.信託の基礎知識
2.高齢者対策としての信託
3.受益者連続型信託
Ⅲ.それでも時代の流れは法人化
1.交際費は増加し景気対策になるか
2.個人の不動産所得と交際費
3.法人税の実効税率 -
本当は東京圏だけが恐い、相続税の大増税!
講演会内容
相続税の申告状況の実態
相続税の改正内容とその影響
1.相続税の計算方法
2.税率の改正
3.小規模宅地の評価減額の特例の改正
4.2世帯住宅と小規模宅地の特例
5.老人ホームと小規模宅地“贈与”の積極的活用による相続税対策
1.贈与税の改正の概要
2.相続税がギリギリで課税される人向けの対策
3.贈与についての誤解
4.贈与の基本的な考え方
5.建物を活用した対策
6.贈与における具体的な注意点
-
財産の「切り離し」による相続節税対策
講演会内容
建物評価に係る相続税法上の問題点
1.相続税法上の評価
2.マンションの評価
3.タワーマンション評価の具体例
自宅敷地を工夫する!
1.2世帯住宅による工夫
2.老人ホームと特例
贈与を活用した相続税対策
1.税率構造の改正
2.相続税がギリギリで課税されるなら
3.贈与についての誤解
4.負担付贈与の課税
5.贈与の時効を考える
6.実効税率と限界税率
信託を活用した相続税対策
1.信託の種類と基本的な考え方
2.所有型法人の問題点
3.賃貸物件を信託すると…
4.受益者連続型信託の活用 -
実例でわかる「相続に強い税理士になるための教科書」
~生前贈与と税務調査実務編~講演会内容
分割と納税方法はセットで考える
1 相続税の納税方法と注意点
2 遺産分割の法的効果と申告
積極的な贈与の勧め
1 根本的な贈与の誤解
2 生活費の贈与
3 賃貸物件の贈与とものの考え方
4 3年内贈与加算の考え方
相続時精算課税の使い方
所有型法人の活用と債権贈与、信託の活用
1 所有型法人とは
2 所有型法人の限界と信託の活用
3 相続が近い場合は債権贈与
税務調査への対応
1 税務署が行う準備調査
2 現況調査と資料せん
3 税理士の役割と対応
贈与の有効性を考える
~実効税率と限界税率~