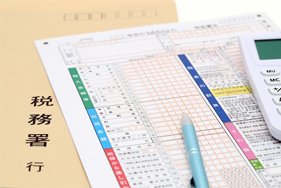ご承知のとおり、「申告納税制度」とは、自ら正しく収入・経費を記録・集計し、税法に従い納税額を計算し、税務署等に申告・納税するというもので、自主的な申告・納税によって納税額が確定することを原則としています。
対象税目としては、国税では、法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税など、地方税では、法人県民税、法人市民税などがあります。
さて、「申告納税制度」は、自ら申告と納税をするという極めて民主的な制度ですが、導入時からうまく機能したのでしょうか。
1.導入時の状況と現状
「申告納税制度」は、日本の税制の柱として昭和22年に導入されました。当時は、敗戦に伴う経済的混乱の中で国民は疲弊し、インフレの高進により所得税等の重税感は大きいものでした。又、昭和23年に税務職員を5万人増員し7万4千人体制にしたものの、職員も不慣れで、税務行政を取り巻く環境は最悪だったのです。
更に、記帳の慣習が十分でない中、昭和23年に個人所得税の申告件数の約70%について、申告怠慢として国が更正決定を行ったのです。そのためおびただしい異議申立てが提出され、税金の滞納も慢性化しました。
導入時の混乱ぶりは想像以上だったようです。
それでは、現在はどうでしょうか。
一つの目安として、租税収入に占める税務調査による追徴税額の割合(以下「追徴税額の割合」と言います)を見てみましょう。
昭和25年度の法人税について見ると、租税収入が924億円であるのに対し、税務調査による追徴税額が287億円となっています。つまり、追徴税額の割合は31%となり、69%が自主的に申告された税額になります。
結果的には何と、昭和25年度は、法人税の租税収入の1/3が、税務調査によって賄われていたということになります。
同様に、平成30年度の法人税について見ると、租税収入が12兆8千億円であるのに対し税務調査による追徴税額が1千9百億円。追徴税額の割合は1.5%となり98.5%が自主的に申告された税額になります。
単純に比較はできませんが、昭和25年度に比べれば、現在の方が、その機能を十分に発揮していると言えるのではないでしょうか。
それでは、何が「申告納税制度」を支えているか、主なものを挙げて見ます。
2.税法上の諸制度
(1)青色申告制度
「申告納税制度」の基本である「適切な帳簿付け」を推奨するため、適切で継続的な記帳と書類の保存を条件に、税法上の特典が受けられるようにしています。
(2)法定調書制度
給与、報酬・料金、不動産の使用料等の支払者にその支払先や支払金額等を税務署に報告させ、支払いを受けた人が適正に申告しているかどうか、税務署が照合するために利用しています。
(3)税務調査
申告内容をチェックし、申告漏れなどが認められた場合には是正することによって、公平な課税と適正申告への牽制効果を狙いとしています。
令和元年度の査察の処理状況は、告発件数が116件、脱税額が92億(1件当り8千万円)であり、税をごまかそうとする事例が後を絶ちません。今後も「正直者がバカを見ない」よう期待したいものです。
3.税理士制度
日本の税理士制度は、ドイツの制度を範として、昭和26年の税理士法制定により整備されました。
税理士法第1条(使命)に「税理士は、申告納税制度の理念に沿って、税務の専門家として適正な申告の実現に努める」と規定されており、約8万人の税理士が国民の良きパートナーとして適正申告に努めています。
4.日本人の気質
日本人は、一般的に礼儀正しく・まじめだと言われていますので、それが「申告納税制度」を支える遠因になっているのかもしれません。
イタリアでは、以前ベルルスコーニ首相が「一定の反則金を払えば、それまでの脱税は大目に見る」という特例を発したことがあります。しかし、イタリアは、宗教改革のもととなった免罪符を売ったバチカンのお膝元だけあって、特に驚くことではないのかもしれません。
これに比べれば、少なくとも日本人の納税意識はマトモな方ではないでしょうか。
上記の諸制度等は、間違いなく「申告納税制度」を支えてきたと思われます。
5.むすび
「申告納税制度」の下では、自主的な申告により納税額が確定すると言われています。
しかし、それは税務署の更正処分がないことを前提とする仮の確定にすぎないとも考えられるので、やはり「税はお上が決めるもの」という感はぬぐい切れません。
そうだとしても、税務調査が「申告納税制度」で果たしている役割を考えれば、条件(税務調査への緊張感)付きの確定でも仕方がないことかもしれません。