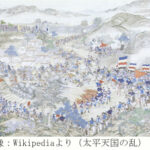安田講堂
2019年1月18-19日は、東大安田講堂事件から数えて50年目にあたる。
だが、年齢の若い一般の読者にとっては、なんだかヘルメットをかぶった薄汚い学生と、警察機動隊が、投石と放水で大喧嘩している映像の印象があるくらいで、その事件がなぜ起こり、当時(1969年-昭和44年)の世相の中でどんな意味があったかをご存じない方も多いのではないか。
事件は、簡単に要約して言えば、当時数多く起きた大学紛争のひとつで、1968年2月に東大医学部で起きた無給医制度をめぐる紛争への大学当局の事態収拾が極めて拙劣であったために東京大学全学の学生たちが怒ってしまい、そのうち最も先鋭的であった東大全共闘の学生たちが本郷や駒場キャンパスの各校舎をバリケード封鎖し、新しく代わった大学執行部の説得もむなしく半年以上も封鎖が継続され、大学入試の実行も危うくなったため、ついに1月になって機動隊による学生排除が行われたが、結局政府の強い意向でその年の東京大学の入学試験は行われなかった。この事件を語った書物は多いが、詳しく知りたい方は、かつて本誌「今月の書棚」が取り上げた、小熊英二「1968若者たちの叛乱とその背景」〈上〉、〈下〉(新曜社刊)あたりをお勧めする。
実は、本稿筆者の父親は、この事件の大学新執行部の一員であったので、筆者は比較的身近にこの事件のことを知る立場にいた。当時高校生であった筆者が思ったのは、なぜ(安田講堂などを占拠した)全共闘の学生達は、最後まで事態の収拾に応じなかったのだろうか、という疑問である。
大学新執行部は、全共闘の7項目の要求事項の内6項目と半分くらいは呑むと言っていたのだし、これが普通の労働組合のストライキなどであったなら、展望のない施設占拠を続けるより、さっさと交渉で手を打って「大勝利」の宣伝でもするところであるのに、ということに首を傾げたのである。実際民青系の学生達や無党派層の学生達は、最初の内こそ「東大民主化」とか言っていたが、1968年の冬になると、全共闘を排除して事態を「正常化」する方向に走っていた。
では、なぜ全共闘は展望のない闘争を続けたのか。それは、1968年の秋、東大の旧執行部が辞任する少し前頃から、彼らのこの紛争(闘争)にかける思いが大きく変化していったからである。
それは、一つには「日本の権力構造の上に君臨し、庶民の果てまでがその権威に幻惑されている、東京大学という存在そのものを、どうにかしない限り、個々の交渉事に勝利してもはじまらない」という「帝大解体論」の台頭であり、もう一つは、「自分たち東大生は、その権威の源泉である東京大学の一員であり、近い将来、官僚や有力企業の幹部、あるいは社会に影響を及ぼす学者などとして、このまま世に出て行く、それは自分たちの上で強権を振るってきた大学旧執行部と同質の存在に自分たちもなることなのではないか」という「自己否定論」の高まりである。この極めてナイーヴではあるが、ある意味では正しい思いに、急進派のとくにノンセクトの指導者達がとらわれたことが、どんな理屈をつけてでも「事態の収拾」「紛争解決」を拒むという、全共闘の頑なな姿勢となって現れたのだといえよう。一方で「正常化」派の学生達は、思想は右でも左でも、やはり「東大の権威」を守るために行動したのだといえるだろう。あれから50年が過ぎた現在も、我が国における「東京大学の権威」は、やや陰りが見えてきたとはいえ、あまり変わっていない。
2019年12月1日