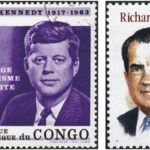不倫
去る2024年10月の総選挙において躍進を遂げた某野党の党首T氏が不倫をしていたことが発覚。某野党を支持する労働団体の代表からは「けじめをつけるべきだ」と苦言を呈されたという報道もある。不倫がスクープされた当初は、「党首辞任」「議員辞職」などを取り沙汰する声もあったが、さすがにそれは少数意見だったようで、この稿を執筆している現在、T氏の「けじめ」は党の倫理委員会だかに委ねられているところらしい。
この稿の筆者は、T氏の支持者ではないが、政治家がいくら公人だからと言って、不倫という最も私的な行いと、公職の進退ということを一緒に論ずる風潮には、違和感を持たざるを得ない。「公私のけじめ」をつけるべきなのは、世論の方ではないかと思うのだ。そこで本稿今月号では、少しだけ「不倫」ということを論じてみたい。
まず定義として「不倫」とは、人間の男女のカップルいずれか、あるいは双方が、家庭があるにもかかわらず、別の相手と肉体関係を持つことを言う。あえて人間と書いたのは、熊や猿の雄は同時に複数の雌と関係を持つことが知られているからである。「不倫」とは文字通り「不道徳」の意味だが、人類社会においても一夫一婦制の道徳を持たない社会は(たとえばイスラム社会のごとく)かなりの比率であるので、上記の行為を「不倫」というのは、人類社会の中でも(多数か少数かは知らないが)ある部分であると言える。ただし、戦後日本社会の価値観では概ね上記の行為は「不倫」とされる。その理由は、主に「家庭があるにもかかわらず」という点にある。配偶者や扶養する子などがいなければ、男女ともに恋愛は自由であるし、恋愛というマーケットの中では、「前のパートナーと切れなければ、次の相手と肉体関係を持ってはいけない」と言うほど厳しい価値観が確立しているわけではない。上記の行為が「不倫」とされる理由は、配偶者を持つ者は、第三者と肉体関係を持たないという法的な「契約」が存在するからである。この契約に違反した者は、行為がばれれば配偶者に「契約違反」を詫びなければならないし、配偶者の意向によっては、契約解除=離婚、あるいは慰謝料を請求されても文句は言えない。筆者が「扶養する子」のことを付記した理由は、「不倫という契約違反」の結果、家庭が精神的あるいは物理的に破壊されれば、子供が影響を受けるからである。逆に「第三者と肉体関係を持たない」という契約が存在する理由のかなりの部分は、家庭の安定を維持するためということもできる。「不倫」は法律上民事の対象ではあっても、刑事罰の対象ではない。T氏が社会的指弾を浴びるのは、民事上の契約違反を犯したからであって、「公人のくせに他人に金を借りたのに返していない」というに近い。
最後に、フランスの某大統領は長年配偶者ではない愛人を持っていて、それは周囲に公知のことであったが、マスコミは大統領の在任中一度もそれを報じなかったという。一夫一婦制の社会でもその程度の寛容さ、あるいは「ゆとり」は欲しいものだと、この稿の筆者は思う。
2025年12月26日