お役立ち情報
COLUMN
クラブATO会報誌でおなじみの読み物
「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!
日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、
その時々の時勢を分析していたりと、
中々興味深くお読み頂けることと思います。
絞り込み:
-

広報
この稿の筆者が、あるビール会社の広告宣伝の担当者であったことは、本欄でも折に触れて書いている。時期によって、所属した部門の名前は広報部であったり、マーケティング部であったり、宣伝部であったりしたのだが、とにかく広報部門というものが、宣伝部門の隣にあった時期が長く、隣の部門の仕事を兼務したり、手伝っていたこともある。
宣伝と広報で、仕事の内容はどう違うか。会社経営に詳しくない方のために少し説明する。宣伝と言うのは、スポンサーとしてお金を払い、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、交通広告、屋外看板などの媒体のスペースを買って、これに自社の商品などの広告原稿やコマーシャルをのせる仕事である。広告原稿やテレビ、ラジオのコマーシャルは広告代理店や制作プロダクションに頼んでつくることもあるが、基本的には自社の言いたいことを消費者の皆様に伝えるのが使命である。一方、広報というものは、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのニュース欄に、自社の情報を載せていただくのが仕事である。新聞記者や放送番組の制作者は、スポンサーのお金の力では自由にならないので、広報部門の担当者は日頃から記者や制作者と仲良くして、自社の事業内容、商品情報をよく理解してもらい、少しでも自社に好意的な記事やニュースを発信していただくのが使命であった。筆者の隣の席の広報課長は、よく「マスコミに接待されるのが宣伝部門、マスコミを接待するのが広報部門なのさ」とか、軽口を叩いていたものだ。
さて、今月はその広報部門(英語では宣伝=advertisingに対して、広報はpublicityという)の話を書く。企業広報の仕事(学校や役所にも共通する)を詳しく分析すると「火消しの広報」、「ばらまき広報」、「仕掛けの広報」の三つの段階がある。
「火消しの広報」とは、当該企業の不祥事(たとえば経営者の背任や脱税、製品のクレームやリコール、事故や火災、社員のセクハラ、パワハラ等々、自社が世間にご迷惑を掛け、頭を下げるべき出来事)が生じたときのマスコミ対応である。記者会見をセットし、経営者の出席を手配し、出席の役員に頭の下げ方の角度を指導し、誤解に基づくマイナス情報が発信されないように、的確な説明を行うことを以て「火消し」という。災いは何時やってくるか分からないから、広報部門には、つねに非常事態に備える準備が必要である。
「ばらまき広報」とは、広報部門のもっとも日常的な業務で、広報資料(業界ではレリース=releaseと呼ぶ)という自社が世間に発信したい情報を書いた書類や写真を記者倶楽部に一斉に配布し、マスコミからの取材に応える仕事である。只ばらまいただけでは取り上げてもらえないので、取材する側との日常のコミュニケーションが大切である。時には特定のメディアに大事なニュースをリークし、大きく取り上げてもらうような寝技も使う。
「仕掛けの広報」とは、イベント、コンクールなどを広報部門側で企画し、マスコミに取り上げてもらうニュース自体を創造する仕事である。たとえば新商品の感想文コンテストなど、ニュースの内容はたわいないものも多いが、広報担当者の企画センスが問われる。
広報の仕事は、宣伝に比べると地味だが、時にはコストを掛けずに社名や商品名を情報発信することもできる。企業人の仕事としては魅力的な部門の一つだ。
2016年9月1日
-

稲荷寿司
このところ、歴史認識だとか、科学技術だとか難しい話が続いたので、今月は庶民一般の大好きな食べもの、稲荷寿司の話を書く。
まず、1837年(天保8年)から書き始められて、約30年(ちょうど幕末まで)書きつながれた喜多川守貞という人の著書「守貞漫稿」という本のことを紹介したい。
この人は、関西生まれの商人で江戸へ出てきて東西の風俗の違いに驚き、以来、時勢、地理、家宅、人事から始まって、娼家の習慣から男女髪型、浴場、子供の遊びに至るまで風俗百般を調査し、東西を比較、精細な図と共に35巻にまとめた。残念ながら、当時著作としては出版されなかったが、明治になってから翻刻されて世に出た。現在、近世風俗を調べる人にとってはもっとも基礎的な文献の一つだという。
その「守貞漫稿」に掲載されているものが、この世の文献に稲荷寿司が登場した初めだそうだ。
それによれば、天保の末年、江戸で豆腐を油で揚げたものを裂いて袋の形にして、そのなかに木茸や干瓢を刻んだ飯を詰めて、すしと称して売り歩いたもの。油揚を狐が好む故に稲荷鮨、篠田鮨などという名を付けたと記されている。至って安い、下世話な食べ物だとも書かれている。
別の説には、お稲荷さんは五穀豊穣の神様で、お米を俵形に詰めた稲荷寿司は、お稲荷さんを象徴したもの(供え物として適切であった?)であるというのもある。この場合狐は、お稲荷さんのお使いだから、稲荷寿司が狐の好物である理由は、「狐が、油揚を好きだから」と言うよりは、稲荷寿司は五穀豊穣の象徴だからということになる。どちらでもよいような話だが、この稿の筆者はかねてから、狐という動物は本当に油揚が好きなのだろうか、という疑問を持っていて、一度試してみたいと思いつつその機会を得ないでいるので、あえて、別の説も紹介した次第である。
稲荷寿司を江戸時代に紹介した別の文献にも、「安い」「下世話」という話は大概書かれていて、新鮮な魚を握った握り寿司を高級として、油揚に飯を詰めた稲荷寿司を下世話とする風潮は、稲荷寿司ができた頃からあったらしい。「天言筆記」という本には、飯の他におからを詰めた稲荷寿司をわさび醤油で食べる話が出てくるそうだ。これなど読者の家庭で容易に試すことが可能なので一度是非、挑戦してみられることをお勧めする。
稲荷寿司の形は、俵形が基本だが、土地によっては、三角形のものもある。西日本の稲荷寿司に三角形のものが多いらしい。助六寿司というのは稲荷寿司と切った巻物が一緒に出てくるものだが、これは歌舞伎の登場人物助六の恋人が吉原の花魁揚巻で、「揚げ」と「巻物」であるという江戸っ子流の洒落である。
さて、以前神様の方のお稲荷さんのことを書いたときにもご紹介したかもしれないが、この稿の筆者の愛して止まない稲荷寿司は、東京六本木のホテルアイビス地下にあった「おつな寿司」の、油揚が裏返しになった稲荷寿司。筆者が宣伝マンであった時代に、よくタレントさんの楽屋見舞いに用いたものだ。現在ホテルアイビスは再開発工事中だが、ネットで調べた限りでは「おつな寿司」は近くに移転して営業しているらしい。
「おつな寿司」
東京都 港区 六本木 7-14-16 03-3401-9953 http://www.otsuna-sushi.com/2016年8月1日
-

水素社会
東日本大震災の後、2011年8月号の本欄で「節電、蓄電、自家発電」と題し、地球温暖化防止と脱原子力のための代替エネルギーについて書いた。その続きの話である。
「節電、蓄電、自家発電」の要旨は、電気というものは水の流れのようなもので、貯めておくことが難しい。もし真夏の昼間電力の10-20%程度でも貯めておくことができれば、発電所の数をかなり減らすことが出来る。脱原子力発電も可能かもしれない、というものであった。具体的な例としては、揚水発電と言って、夜間電力で水をポンプで高所に汲み上げ、昼間その水をダムから落として水力発電を行う術などを紹介した。
さて、世間でよく知られる、太陽光発電や風力発電などには、一つの欠点がある。それは、不安定で、要るときに使えるとは限らないということである。真夏の昼間、ものすごく暑い日に太陽光で発電することは出来そうだが、風が吹かなければ風力発電は出来ない。
つまり、代替エネルギーによる発電は、人々が電力を欲しいときに、当てにならないことがあるという訳で、その欠点が原子力発電推進論の一つの論拠になっている。ところが、電気を貯める(電池代わりの)手段として、水素というものが最近有力になってきた。
水素は、地球上に水という形で普く存在している。電力の原料としては木材、石炭、石油などの炭素系の化石燃料や、ウランなどの核燃料に比較しても、入手はきわめて容易である。とくに我が国の様な海洋国家の場合、国の四囲は水だらけである。
さて、よく知られているように水の構成要素は水素原子2個と酸素原子1個である(H2O)。水の分子の水素と酸素は、固く結合しているのだが、電気を与えると分解する。これを水の電気分解という。水が電気分解すると酸素は大気中に放出され、残りは水素ガスになる。その水素ガスをタンクに貯めておいて、電力が欲しいときに大気中の酸素と再び結合させると水になる。水素と酸素が結合して水が出来るときには、電気分解と逆の原理が働いて、電気が放出される。石炭や石油を燃やす(酸素と結合させる)と二酸化炭素が大気中に放出されるのだが、まあ簡単に言えば水素を「燃やして」も水しか出てこない。その上結構なことには、水素と酸素が結合し水となるときに、電気が出てくるのである。一つ問題があるのは、この水素燃料電池の仕組みは、現在の所まだロスが大きい。最大でも、水を電気分解するときに使った電力の60-70%くらいしか、回収できない。
現在の技術では、水から水素をつくるよりも、むしろ天然ガスから水素を取り出す(改質という)方が、効率は良い。既に市販されている「エネファーム」などの水素発電装置は、天然ガス改質法を用いているが、これだと有限の化石燃料を使うし、改質の過程で二酸化炭素も発生する。
やはり、将来の技術の本命は、水の電気分解であるだろう。水の電気分解効率が向上し、且つ水素ガスという一種の危険物を都会の中で安全に管理する技術が進めば、太陽光や風力発電で得た電力を用いて、水を分解して水素を貯め、その水素を電力が欲しいときに水に戻して電力を取り出すという方法が、代替エネルギーの本命となることだろう。
注:本稿は、「東芝が目指す水素社会」のホームページに取材させていただいた。http://www.toshiba.co.jp/newenergy/2016年7月1日
-

無線、暗号、コンピュータ
無線通信というものと、コンピュータ(古い言い方をすれば電子計算機)というものには深い因縁がある。今月は、それについて述べたい。
無線通信は、イタリア人グリエルモ・マルコーニが19世紀の終わり頃に発明したとされる(異説もある)。マルコーニが無線通信の事業化に乗り出してすぐの頃に、タイタニック号の沈没事件(1912年)が起きた。無線通信は、この時初めて実用として活躍した。それから、50年くらいの間、無線通信は電信といって、トン・ツーの組み合わせで綴るモールス符号によって行われてきた。真珠湾奇襲の「トラ・トラ・トラ」(我奇襲に成功せり)の信号もモールス符号である。無線電話は、第二次大戦中に一部で使われてはいたが、一般社会に普及するのは第二次大戦後である。
無線通信というものは一定の周波数帯の受信機を持っていれば誰もが受信できるので、傍受と言うことが基本的に可能である。そこで、人々は暗号を用いて通信の秘密を守ろうとした。異地点間のA(攻撃隊の隊長)とB(航空母艦座乗の司令長官)の間で「トラ・トラ・トラ」という信号は「我奇襲に成功せり」の意味であると予め了解しておいて、発信すると、AとBの間では意味のある会話が成立するが、他人が傍受しても何の意味だかわからない。これが暗号の原理である。暗号の歴史は人類の歴史と同じくらい長い。が、暗号は第二次世界大戦の頃には、かなり高度な数理(アルゴリズム)を用いた複雑なものとなっており、暗号鍵を知らないで解読するのは、かなり困難になった。そこで敵方の暗号を解読するのに二つの技術が生み出された。一つは、窃盗や色仕掛けで暗号鍵が記載されている乱数表や、暗号文を作成するタイプライターに似た機械を盗み出すスパイ術であり、もう一つは力業で、大量の計算をして数理で暗号を解読する技術である。後者の力業はとても人間の手に負えないので、機械に頼ることになる。この暗号解読を力業でやってくれる機械として発明されたのが、電子計算機なのである。電子計算機は、英米で発達し、第二次大戦における連合国側の暗号解読技術は、優れたスパイ術と相まって、枢軸国側を遙かに凌いだ。ミッドウェー海戦にしろ、山本五十六司令長官の機上戦死にしろ、日本がアメリカに負けてしまったかなりの要因は、無線で米軍が傍受した日本海軍の暗号通信文を、米国側に解読されてしまったことにあると言っても過言でない。日本側も、米軍の暗号を解読するためにそれなりにがんばったが、残念ながら人力は電子計算機の能力の及ぶところではなかった。
その後、無線通信とコンピュータは、別れ別れに発達をすることになった。無線技術は、電信から電話(音声)へ、そしてテレビ(画像)放送へと発達した。一方、コンピュータ同士をつないで有線で通信する技術(コンピュータ通信)は後にインターネットへと発達した。そして今、無線とコンピュータの技術は再び出会おうとしている。そう、今貴方が使っているスマホが、その出会いの証である。そしてこの再会の仲立ち役は、暗号技術である。暗号こそが、貴方のスマホの通信秘密を守る、大事な仲人なのだ。
2016年6月1日
-
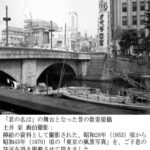
忘却
「忘却とは忘れ去ることなり。忘れ得ずして忘却を誓ふ心の悲しさよ」
菊田一夫の名作、NHKラジオドラマ「君の名は」冒頭の有名なフレーズである。
と、言っても、放送開始は1952年(昭和27年)であるから、すくなくとも現在70歳くらいから上の方でないと、上記の台詞をナマで聴いたのを覚えておられることはないだろう。
このドラマでは、忘れようとしても忘れられない人、というのがテーマであって、忘れることより忘れられないことの方に重点がある。世の中は戦後復興に向かい、国はまだ若く元気であった。封建的な家族制度のくびきにつながれた女性の主人公と、形式上は不倫なのだが純愛を貫く男性の主人公。真知子と春樹は、ともに新しい国、社会、個人の自由の象徴であった。まあ、要するに国民は、エネルギーに満ちて健康であったのだ。
そこには、高齢化、認知症、忘れたくなくても忘れてしまう問題というのはまだなかった。
その次に来るのは、高度成長。「都合の悪いことは、飲んで忘れてしまおう」、という無責任時代。「ちょいと一杯のつもりで飲んで、いつの間にやら、はしご酒」「わかっちゃいるけどやめられねぇ」は、後に都知事となった青島幸男の作詞で植木等が歌ったご存知「スーダラ節」。この時代の日本は、プロジェクトX、「ものづくり日本」の時代でもあった。が、一方で公害垂れ流し、川も空も真っ黒け、手抜き工事もやり放題、後先を顧みず原子力発電に邁進する「行け行けドンドン」の産業優先時代でもあった。忘却について言えば、高度成長期の日本は、深刻な経験や問題を忘れる能力のある者が優者で、過去をいつまでも忘れられない者が負けていく、そんな時代であった。やがて、バブル。忘れちゃいけないことも平気で忘れてしまう。ノリと軽さと無駄遣いの時代が来る。ここで日本は決定的に国を誤る。せっかく豊かになった富を、ストック(広い意味での社会資本、社会インフラ、研究投資、芸術文化や教育教養も含めて)に転換せず、ひたすらフロー(社会における金融の流量)を追求した。不動産投資、金融投資、マネーゲーム。つまりはフローの方が、もの作りや研究開発よりも早く結果が出る。出世につながる。目の前の刺激が、ほんとうに大切なことを忘れさせてしまう。人々はついでに純愛も忘れ、ひたすら欲望の充足に走った。
バブル崩壊。高齢化社会、人口減少。自分で何をして良いのかわからない惚けた経営者が、「若い人に任せる」と言って部門ごと責任を丸投げし、結果責任だけを追及するようになり、日本国中がヒラメ社会化した。「やってみなはれ」でも「だめならクビよ」という社会は、やがて大量の非正規雇用者を生み出した。それは、セーフティネットなんてどこにもない、ひどく危なげで不安な社会でもある。高度成長の戦士は恍惚老人と化し、忘れたくなくても忘れてしまうのは、日常の食事や出来事、身の回りの地図と位置。はいかい、行方不明の老人を社会がどのように守るのか、高齢者の忘却は、社会共通の大問題である。
そして、今、日本の国家自身が、70年前の戦争の死者を忘れ、他国に犯した過ちを忘れ、かつて世界の人々に対してした崇高な約束を忘れようとしているのではないだろうか。
2016年5月1日
-

上座部仏教
縁あって、ミャンマーに出かけた。
この国は、上座部仏教(南インドやスリランカを経てミャンマー、タイ、ラオスなどに伝わったいわゆる南伝仏教)の世界である。5千万人の人口に対して20-30万人の出家僧侶がいるという。ほんとうの僧侶のほかに、男性は一生に一度以上、暫時剃髪出家して寺院の戒律に身を委ねる。僧侶は、厳しい戒律を守って、午前中しか食事をせず、金銭や女性に触れないという暮らしをする。僧侶の生活は、老若男女市民すべての寄進によって賄われる。この国では、寺院に寄進をすることが人生の生きがいである。社会の中で競争し、働いて、富を得ても、その富を寺に寄進してはじめて、働いた実感を得ることができるのである。一方寺院では、僧侶はきわめて禁欲的に生きているので、寄進された富はなんらか社会に還元されるのであろう。上座部仏教は、日本では20世紀の半ば頃まで、小乗仏教と呼ばれた。それに対して、チベット、中国、朝鮮を経て日本に伝わった北伝仏教の方を大乗仏教と自称した。その後、1950年コロンボで開催の世界仏教徒会議において大乗側が南伝仏教を小乗と呼ぶのは蔑称であるということになって、上座部仏教という名前が使われるようになったという。
では、南伝仏教と北伝仏教の教えの違いは何処にあるか。この稿の筆者は、仏教徒の家庭に育ったわけではないので、あくまでも外側から見た筆者の理解を以下に記す。お釈迦様にとっての課題は、輪廻転生を繰り返すこの世の業(カルマ)から解脱することであり、その方法は瞑想と禁欲、修行であった。具体的にどんな修行をなさったのかは諸説あるが、とにかくあるときお釈迦様は悟りを開かれたのである。この時点で、悟りを開いて業から解脱することは誰にでも可能なことではなかった。悟りとは、一部の少数者が厳しい修行を経てはじめて到達できる境地であった。お釈迦様のあと、その跡を慕って自分も悟りの境地に至ろうと努力する人々が生まれ、仏教団が形成されるようになった。
そして仏教が世に伝播していく過程で、戒律を地域の慣習にあわせて緩やかに解釈しようとする派(たとえば、食事は午後にとっても良い、とか)とお釈迦様の方法を細部まで守ろうという派が分裂した。前者は、次第に一部の特別な人だけが悟りを得るのではなく、お釈迦様の教えを広く遍く普及させて多くの衆生を救済しようとする傾向に走り、後者はあくまで厳しく修行をする僧侶達を衆生が支えることを以て、一般人の心の平安が得られるとする傾向を持つようになった。前者が北伝仏教、後者が南伝仏教である。北伝が自らを大乗仏教と呼び、南伝を小乗と蔑んだのは、北伝仏教が大衆も乗れる大きな乗り物であるのに対して、南伝仏教は一部の特別な人しか乗れない小さな乗り物であるとしたからである。一方で、「大乗仏教」が極まれば、南無阿弥陀仏六字の名号を称えるだけで、何の修行をしなくとも救済が得られるという教えにもなる。どちらが正しいと言えないが、ミャンマーの国中に建てられたパゴダや寺院を見ると、人々が寄進という価値観を共有することによって、社会の富が循環するというのも、一つの大きな思想であると思った。
2016年4月1日
-

アジアの近代(続)
前号では、アジアの近代化には、軍事、経済、政治等複数の側面があることを述べた。
この内軍事の近代化、経済の工業化(資本主義化)については今日21世紀の北東アジア諸国は達成の途を歩んでいると言っても差し支えない。これらの近代化は概ね世界共通のものであり、とくにアジア的な特徴があるわけでもない。問題は、政治の近代化である。アジア諸国の内、欧米的な意味での議会制民主主義と自由、平等、博愛原理に基づいた政治制度を完全に達成した国は、日本しかない。東南アジア諸国は概ね欧米モデルの政治制度を標榜してはいるが、実際には、開発独裁であったり、軍部統治であったりで、議会と選挙による政権交代が常態の国はきわめて少ない。韓国あたりがだいぶ欧米モデルに近づいてはいるが、政党政治の内実は、まだ日本の大正期政党政治のレベルくらいに見える。中国や北朝鮮の政治制度がどうなるのかは予断を許さない。
さて、問題は、政治制度の近代化について、欧米と異なるアジア的なモデルが存在しうるか否か、ということである。中国の革命家孫文は、かつて西洋帝国主義の政治を覇道と呼び、対するに東洋的な王道政治の実現を説いた。しかし、その王道政治の思想原理、政治制度のモデルなどを中華民国で具体化することは出来なかった。日本も、かつて満州統治や大東亜共栄圏の制度設計において「東洋的王道」を掲げたことがあるが、それは西洋的な個人主義、競争原理の否定と統制経済、軍部による全体主義的な指導を正当化するに過ぎず、独自の政治原理を提起するには至っていない。また、印度の革命家ガンジーも、非暴力抵抗主義という反権力の方法を提案することは出来たが、その思想を統治(あるいは自治)の原理にまで敷衍することは出来ていない。21世紀国際政治の一つのエポックである、イスラーム原理主義もまた、西洋近代に対置しうるあたらしい政治原理や制度を示すことは出来ず、ただ預言者への回帰を説くだけに見える。
現実社会を離れた思惟や、文化芸術において、東洋は十分西洋に拮抗しうる膨大な歴史的蓄積を有している。だが、要するに、21世紀の今日に至るも、軍事や経済の近代化と同様、政治の近代化について、西洋モデルを超える東洋的なモデルは示されていない。
それは何故か。短い紙数で筆者が感じていることを記すと、政治制度も経済のあり方も、結局は技術革新の産物であるというに尽きる。西洋近代の資本主義の根っこに仮にキリスト教文明があったとしても、西洋近代の政治思想や資本主義経済、さらには帝国主義や植民地支配を生み出したものは、産業革命による技術革新だったのではあるまいか。
東洋の思想は、産業革命に匹敵する技術的な裏付けを持たなかったのだ。
そうであるとすれば、今日、インターネット時代の情報技術の革新こそが、現代社会のあり様を決める根幹である。私たちは、まさに洋の東西を問わず、情報技術の革新が生み出すところの経済制度、政治制度、社会思想の、近代を超えた世界共通モデルをこそ設計すべきなのではないか。もはや、アジアの近代にこだわるべき時代ではない。
2016年3月1日
-

アジアの近代
以前「歴史認識」という題で、日本のアジアにおける侵略や戦争について、日本人が第一次世界大戦後の国際法秩序しか問題にしないのに対して、中国、韓国の人々は日清戦争やさらには江華島事件などに遡って問題にしているということを書いた。
日本の言い分は、第一次世界大戦までは、よかれあしかれ帝国主義の時代。植民地保有も国際法に照らして合法だったというものだ。が、植民地にされた、あるいは侵略された側の言い分は、そもそも近代の初めから西洋諸国がアジアやアフリカの諸国を支配してきた歴史そのものが「まちがい」なのだし、西洋諸国の尻馬に乗って似たような振る舞いをした後進の近代国家日本などは、もっと「けしからん」ということになる。
その「けしからん」という思いの中には微妙に華夷秩序意識というものが働いている。
ところが、近代西洋諸国が、アジアを侵すようになると、小国日本は勇躍華夷秩序を脱し,アジア諸国の中でいち早く近代化を遂げた。東夷の国と思われていた日本は、いつの間にか西洋諸国を模倣するようになり、ついには近代化された軍隊を以て韓国を支配下に治め、中国にも筒先を向けるようになった。未だ近代に目覚めきれなかった、19世紀末期の中国、韓国の人々は、日本を夷狄と見下している内に、華夷秩序を破壊されて立場が逆転し、今度は近代化した日本という存在に脅かされるようになってしまった。
日本も、中国も、韓国も19世紀西洋列強のアジア進出に脅かされた。それらの国の青年達は、皆、自らも近代国家とならねば、独立を保てぬ事を思った。だが、どこまで自らを近代化するか、どの程度西洋に近くなるかについて、同じ国の中でも、一人一人の思いは異なるものがあった。最も異議の少なかったのは、軍事技術の近代化である。軍艦、鉄砲、近代的軍隊がなければ侵略されてしまう。だが、その軍事技術さえ、刀槍や拳法で代替できると称える者も居た。経済の仕組みの近代化には強い反発があった。工業化、資本主義化とは新たな支配と被支配の関係をつくることであったし、農村的秩序や服装、生活から学問、芸術に至る東アジア的文化の破壊につながるものでもあった。さらに政治における近代化は最も異議が多かった。自由、平等、博愛、議会制民主主義は東アジアの伝統に馴染みにくかったし、第一、西洋の理想主義的政治思想も、西洋人の野獣のような振る舞いの前では説得力に乏しかった。アジアの青年達は、この200年ほどの間、なんとか西洋的近代主義に対置しうるアジア的価値観を模索しようとした。が、結局その試みはあまり成功せずに終わったと言えるのではないか。~この項続く。
2016年2月1日
-
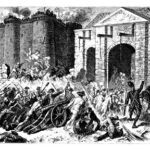
革命暦
暦の話である。
暦については、太陰暦と太陽暦、天文学の進歩に伴う各種改暦の話題等があるが、これらについては一応世界的に決着がついていて、1582年にローマ法王グレゴリウス13世が制定したグレゴリオ暦(1年は、平年365日、閏年366日、閏年は4年に1回だが、400年に3回4の倍数年なのに閏年のない年がある)が世界標準となっている。漢字文化圏では、これを西暦と呼んでいる。
キリスト教に異論がある国や人でも、暦法自体は概ねグレゴリオ暦の数え方を踏襲している。
だが、暦法はそうであっても、紀元、年号、一年の中での月、週、曜日の数え方等については、「何もローマ法王の言う通りにしなくたって良いじゃあないか」と考える者がその後も頻出している。
中国の黄帝紀元、我が国の神武紀元などは「キリストよりこちらの方が古い」と自己主張するためだけにあるようなものだ。が、中華民国暦、ソビエト連邦暦などは、ある国の革命によってそれまでの体制が覆され、政治や経済に関する主義主張が新たになったばかりでなく、庶民の生活文化面でも刷新が必要と言うところから、暦を新たにした「革命暦」である。
今日はその中から、革命暦の本尊と言えるフランス共和暦を、少し詳しくご紹介しよう。
フランス革命暦は、フランス語でCalendrier révolutionnaire français、その別名である共和暦は、Calendrier républicainという。1792年9月22日フランスではブルボン王制が廃止され、翌年1月21日には前国王ルイ16世が処刑された。その年、1793年の11月に制定されたのが共和暦で、フランス共和制が発足した前年の西暦9月22日を紀元(共和暦元年1月1日)とした。
共和暦制定の目的の一つは、暦法ではグレゴリオ暦を踏襲しながらも、七日一週制も含めたキリスト教の生活文化を排して、できるだけ合理的、近代的なものに置き換えようとするものであった。
その核となる考え方が、十進法の導入。平年は365日だが、1ヶ月は30日、12ヶ月は360日、残りの5日(閏年では6日)はどの月にも属さない休日として「正月」(だが元旦が西暦9月22日なので秋たけなわの陽気の良い時期)直前に配置された。週と曜日は廃止され、かわって10日間の「旬」が生活の単位となった。
フランス共和暦でもっとも秀逸なのは、12の月の名前であろう。[秋] Vendémiaire ヴァンデミエール(葡萄の月) 、Brumaire ブリュメール(霧の月)、Frimaire フリメール(霜の月)、[冬] Nivôse ニヴォーズ(雪の月)、Pluviôse プリュヴィオーズ(雨の月)、Ventôse ヴァントーズ(風の月)、[春] Germinal ジェルミナル(芽の月)、Floréal フロレアル(花の月)、Prairial プレリアル(草の月)、[夏] Messidor メスィドール(収穫の月)、Thermidor テルミドール(熱の月)、Fructidor フリュクティドール(果実の月)とすべて韻を踏んだ、農業にちなんだ洒落た名前がついている。
さらに念の入ったことに、一日一日にも、たとえば葡萄月28日はトマトの日とか、霧月5日はガチョウの日とか、花、野菜、果物、鳥、家畜、農機具等の名前がついている。
この暦は、1806年皇帝ナポレオンによって廃止されてしまう。その原因となったのも行き過ぎた十進法の導入だったとか。共和暦では時間も1日は10時間、1時間は100分、1分は100秒というおよそ庶民の生活と異なる時を導入しようとして失敗した由。革命も、暦も、やり過ぎは良くない。
2016年1月1日
-

ラジオドラマ
筆者は、学生時代、放送研究会に所属して、ラジオドラマの脚本を書いたり、演出をしたりしていた。もう三十年近く前の話だが、それでも当時の社会は、すでにテレビ全盛の時代になっており、ラジオドラマなどと言うものは、民放では特別編成の時だけ、NHKがかろうじて、週に二本放送している程度だった。
その時代に、私達学生が、映像を用いたテレビドラマではなく、音声だけのラジオドラマに固執していた理由は、本当のところを言えば、単にカネがなかっただけのことなのかもしれないが、自分達では、一応もっともらしい理屈をつけていた。その理屈とは、「私達の創造する芸術は、イマージュの完全な伝達を求めるものではなく、個々の聴き手を音声で刺激して、聴き手各自が想像力でイマージュを創りあげるのを助けようとするものだ」というものだった。
たとえば、サウンド・エフェクト(効果音)が、怪しげな足音を流す。足音は向こうから此方へやってくる。ドラマの筋から推理すると、どうも主人公を逮捕しに来る警察官らしい。さて、その警察官が私服なのか、制服なのか、公安なのか刑事なのか、どんな顔をしている何歳くらいの、そもそも男なのか、女なのか、それらはみなドラマの作者の側が「与える」のではなく、聴き手に「想像してもらう」訳である。もしテレビや映画などの映像芸術であれば、近づいてくる足音の主をカメラが捉えた瞬間に、足音の主の像は「与えられて」しまうのだが、ラジオドラマは、聴き手に考えてもらい、想像してもらうのである。だから音声によるドラマは、映像によるドラマより聴き手に知的営為を求める。それゆえ知的な聴き手にとって面白いかもしれないが、疲れる。大衆が映画からさらにテレビへと流れていったのは、まさにその疲れるのが嫌で、受け身で「与えられる」ことを求めたからかもしれない。
ともあれ、学生の屁理屈にしては、我ながら、なんとも奥ゆかしい理屈ではあったと思うのだが、私達は、「だから音声によるドラマの試みにこだわりたい」と大まじめに言い合っては、つたないラジオドラマの制作に励んでいた。
さて、この理屈は、「他者とのイマージュの共有を求める」というあつかましい姿勢から、一歩下がって、おのれが創造したイマージュの情報量をわざと落として、他者の想像力を刺激しようとすると言う点で、詩や、俳句の世界にも大きな示唆を与えるのではないかと思う。
芸術家が自己の内部にかたちづくった世界そのものを、他者に「伝えること」=移し植えることを一度断念して、いくつかのイマージュの要素だけを他者に伝達し、それを受け止めた聴き手は、伝えられた要素を手がかりに、自分のイマージュの世界を「再構成する」。ラジオドラマの聴取者は、ひとりひとり別のドラマを自らの内に再構成しているのであって、「同じドラマ」を聴いているのではない。
そうした、間接的なコミュニケーションの有り様は、詩歌の世界では俳句が、映像の世界ではモノクロームの静止画像が担っているのだと思う。
五七五僅か十七文字の句が切り取る、世界の一部。モノクロームの静止画像が切り取る「対象に寄った」クローズアップも世界の一部分である。それは示されたものの底辺に広がる大きな世界を、単に象徴するのではなく、顕れ示されたものの底に、様々な受け手のイマージュをルーツとして持っているのではないだろうか。ラジオドラマの奥は深い。
2015年12月1日
-

猫まんま
本誌に、二回にわたって犬族の会議について書いたところ、発行元の税理士法人内に猫の愛好家がおられて、「あれだけ犬を取り上げたのだから猫も書いてほしい」という要望が、編集担当者を通じて寄せられた。
正直に言うとこの稿の筆者は、猫と暮らした経験がない。犬と猫とどちらが好きかという問題ではなく、生まれたときから身近に犬がいたのであって、猫とはほとんど個人的な友好関係を結ぶに至らなかっただけである。かろうじて、小学校時代の学友次郎君が飼っていたトラという名の猫と、母方の伯母の家にいたやはりトラ猫(筆者より年長のおばあさん猫だったように思う)だけが、筆者のことを個人として認識してくれて、先方の機嫌の良いときはフニャアと挨拶にすり寄ってきてくれた。が、猫は元々犬より気まぐれだから、次郎君の家や、伯母の家に遊びに行っても、猫が遠くの方であくびをしていて全く筆者に関心を示さない日もあった。
筆者の猫とのつきあいはまあそんなものなので、どうも猫について何かを書けるだけの材料がない。と、思ったら、ひとつだけ「猫まんま」については書けそうだということが分かったので、それで文責を塞ぐこととする。
「猫まんま」とは、文字通り猫が食するご飯のことである。キャットフードなどという商品が市場に出回るようになったのは、第二次世界大戦後のことであるから、それまでの日本では、家庭に飼われている猫は、概ね人間のご飯のお下がりを食べて暮らしてきた。敢えて残飯とは言わない。猫好きの人はそれなりに心を込めて人間のご飯を調進していたはずである。それが「猫まんま」である。「猫まんま」には定義がある訳ではなく、猫用に人間の食べものをアレンジしたもの、というに過ぎない。が、猫の立場になれば、おかず、ご飯、汁が別々に出てきたとて、箸を持って食べる訳ではないから不便である。よって、「猫まんま」とは概ね人間の食事をall in oneにしたものであると言える。
さて、関西と関東では、「猫まんま」のイメージがちがう。関西の「猫まんま」は、汁掛け飯(先般「味噌汁」の項で筆者が「ポチ飯」と称したものに近い)、関東は混ぜご飯(とくに鰹節を混ぜたご飯)のことを「猫まんま」と呼ぶらしい。なぜ関西がwetで関東がdryなのかはよく分からないが、日本史の流れから想像するに、まず汁掛け飯が生まれ、後に混ぜご飯となっていったと考える方が自然ではないかと思う。
この稿の筆者は、wet、dryいずれの「猫まんま」も大好きである。とくに独身時代は、よく風邪を引くと自分で「猫粥」という、卵と鰹節とが入った粥に醤油で味付けしたものをつくって食べていた。また、混ぜご飯の方も、シラスと鰹節入り猫まんま、猫まんま炒飯、青海苔とおかかの猫まんま、鰹節生卵かけご飯等々すぐに豊富なバラエティーを思いつき、つくることができる。
ただ、猫の健康を考える立場からは、注意を要することがある。猫は、人間はもちろん犬に比べても炭水化物の消化能力が低い。また人間と比較すると腎臓の能力が低いので、人並みの塩分を摂取すると過剰な負担がかかるのだそうだ。だから、人間の食する米飯を(汁掛けにしろ、混ぜご飯にしろ)人間の味付けで猫に与えることは、猫の健康には良くない。人猫共貧しかった昔はともかく、猫も食べたいだけ食べられるようになった現代においては、猫向きの、薄い味付けの、炭水化物の少ないキャットフードの方が、猫には良い。「猫まんま」は人間が食べれば良いのだ。
タマネギ中毒に注意!タマネギ、ニンニク、ニラなどは「猫まんま」に入れてはいけない。
タマネギ中毒(From Wikipedia) タマネギなどの摂食を原因とする犬、猫や、ウシなどの食中毒のことである。サルなどは、タマネギ中毒にはならない。タマネギ、ニンニク、ニラなどのネギ属に含まれるアリルプロピルジスルファイドなどがヘモグロビンを酸化させることにより、溶血性貧血を起こすことによるもの。タマネギ中毒起因の溶解性貧血が発生すると、赤血球内のカリウムが血液中に流出し高カリウム血症に伴う死亡の危険が高まる。2015年11月1日
-

自己目的化
麻雀という遊びが廃れて、もはや四半世紀近くになるだろうか。我が国がバブルの頂点に向けて、まっしぐらに高度成長の道を突っ走っていた時分には、世の中の会社員は、この暇つぶしゲームに滅相もないお金を賭けて楽しんでいた。最近では、四人面子がそろわないとできないような遊び事は流行らない。現代の若者は、専らゲーム機に向かって一人で格闘しているし、賭け事の好きなオジサンやオバサンだって、近頃はパチンコという一人遊びにこそ熱中するが、丁半賭博、チンチロリン、ブリッジ、花札、麻雀と何人かの仲間でやるようなアナログゲームはみんな廃れつつある。
さて、麻雀好きの読者ならよくおわかりと思うが、麻雀の下手な人の代表選手は「手作りにこだわる」人である。麻雀を知らない方のために少し解説すると、麻雀というゲームには、色々な「役」という配牌の組み合わせがあって、それらの役のどれかを完成して早く上がった人が一局の勝利者となる。ついでに言えば、誰かが勝利者となるためには「振込み」といって、自分が捨てた牌が勝利者の「役」を最終的に完成させる敗者がいる。つまり四人の内一人が勝利者となると大概は一人が敗者となる仕組みである。敗者は勝者に「役」相応の点棒を差し出すことになっている。それを、八局とか十六局とか繰り返して、総合点を競うゲームである。「役」には、有名な大三元(白牌が三個、発牌が三個、中牌が三個そろったもの)とか、緑一色といって手許の十四牌が全部緑色で他の色が混じっていないもの、字一色(東南西北白発中の各牌が二個宛そろったもの)などがある。が、此処に書いた「役」は皆とても珍しいもので、上がれる確率はそれほど高くない。相当麻雀好きな人でも、(インチキしなければ)一生に何回か上がれる程度である。
では、「手作りにこだわる」人とはどんな人か。開始時に配られた牌を眺めて、こうした希少な「役」ができそうに思えると、高得点かつ上がるのが困難な「大役」を作り込むことにひたすら専念し、もっと早く上がれそうな安直な「役」を顧みない。周囲の競争者がどんな「役」で上がろうとしているかなども全く見えなくなる。その結果、高価な「大役」がもう少しで完成するというときになって、自分が捨てた牌が他人の当たり牌(「役」を完成させる牌)となって「振込み」、敗者となってしまうのである。
「手作りにこだわる」人は麻雀に負けても実は何とも思わない。ゲームに勝つことより、生涯一度の「大役」をつくったという快感を追求するのである。実はこの稿の筆者もその一人で、失う金より、得られたかもしれない夢の方がはるかに魅力に思える。だが考えてもみよう。人類は、生殖という行為を自己目的化して「恋愛」文化を生み出し、生命維持のためにエサを口に入れる行為を自己目的化し「グルメ」探求文化を生み出したのだ。
麻雀の下手な者とは、思い適わぬ女性を求め続けて子孫を残せない男とか、究極の美味を求めてフグに当たる男のような者ではないか。人類が他の動物と違うところを持つとすれば、それは自己目的化による文化の形成である。「手作りにこだわる」ような人こそ、人類の名誉をもっともよく担っているとは言えないだろうか。
2015年10月1日
