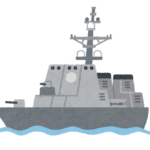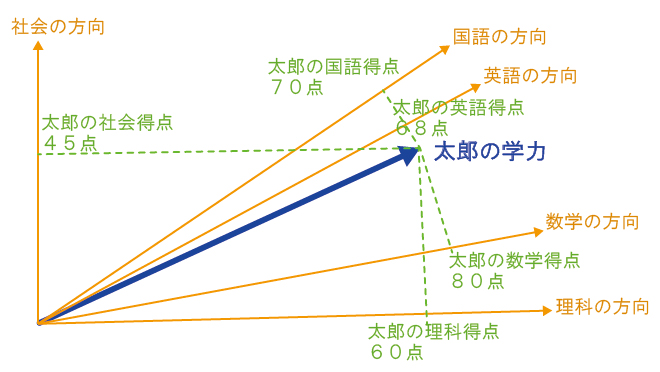徳川家康
戦国時代における各地の大名達の興亡劇は、日本歴史の中でももっとも物語性に富んでいて、時代小説の半分以上は、この時期を題材にしていると言っても過言ではない。そして戦国期のことを少し詳しく調べてみると、日本中が一つの大きなトーナメント戦を展開していて、あたかも甲子園のごとく地区予選、甲子園の一回戦、準々決勝、準決勝、決勝と進んで、最後に徳川家康という人が優勝したというようにも読めるのである。この家康という人は、しかも地区予選でも殆どシード権を持っていなくて(豊臣秀吉ほどではないが)、地区予選の最下層に近いところから勝ち上がってきた。そして各々の時期で、家康は自分の生きがいや振る舞いを微妙に変化させてきたように見える。
まず、竹千代期。(誕生1543年-)彼の実家の松平氏は、西三河の土豪中の有力者ではあったが、松平家自体が二十数家もあって、その中には竹千代の実家にとってかわる力がある家もあった。つまり周辺の国人衆(後に服属の度が強まって「三河以来の旗本」になる)とそれほど変わらぬ力しかなかった。東三河の戸田氏に騙されて織田家に売り飛ばされたり、捕虜交換で今川氏の人質になったり、軽い扱いを受けたのも松平家の実力がその程度であったことを示している。幼時の竹千代はその現実を受け入れるしかなかった。
松平元康期。(元服1555年-)駿府の人質であったこの時期、彼は太原雪斎に見いだされ、後の築山殿を妻として、今川氏の縁戚に取り立てられ、今川の次世代の有力な部将候補となったものとこの稿の筆者はみる。今川軍団にもこの時期「武士の専業化」の萌芽が見られⅰ、元康にとっては、何か自分の新しい未来が開けたような気持ちだったのではないか。
清須同盟期。1560年桶狭間の戦いの直後、松平元康は駿府に帰らず、今川氏の「捨てた」岡崎城に入城して独立。西三河の国衆を束ね、やがて敵対していた織田信長と同盟を締結する。
岡崎入城の決断は、今川軍団内での自己の未来を捨て、西三河の国衆の武力を背景とする小領主としての自立を選ぶもので、相当の迷いがあったと想像される。それでも、元康が岡崎の国衆を選んだのは、義元の死によって今川軍団における自分の未来が見えなくなったと感じたこと、あるいは義元の後継者氏真との人間関係に齟齬があったことも想像される。三河の国人側から見れば元康の独立は、今川氏支配による収奪にあえいでいた彼らの現実からの解放を意味し、歓迎された。元康は、今川義元の偏奇「元」を捨てて家康と名告り、やがて織田氏の仲介で朝廷から三河守の官位に叙せられ、徳川家康と称するようになる。家康は東三河をも勢力圏に入れて戦国大名の最小単位である「国」の領主となる(いよいよ甲子園に出てきた)。その後は織田信長の天下統一事業に駆使されるようになるが、家康は誠実に同盟を守り一度も信長を裏切らなかった。
武田対戦期。(浜松移転1570年-)左記は通常清須同盟期に含まれるが、筆者は三河と言う小国の領主から、遠江を得て東海地域の(弱小だが)戦国大名となったと言う意味で、トーナメント戦の重要な一階層を進んだと見る。この時期の家康は織田氏に服属しつつも名目上は同盟者として、強敵武田氏の西への侵攻を阻止する役割を全うした。1572年三方原では破滅に近い敗北を、1575年長篠・設楽原では織田氏との連合の下で決定的な大勝利を経験した。だが、その後1579年長男信康を舅信長の命で切腹させるという大事件が起きる。
ここからについては、次号を参照されたい。
ⅰ 元康だけでなく、たとえば桶狭間で戦死した井伊直盛などもこうした国人から切り離されて
今川氏に近侍する部将の候補だったのではないかと、この稿の筆者は考えている。
2023年12月27日